タイにおける遺言について

タイでは、日本とは異なる法制度のもとで遺言が管理されています。
そのため、適正な形式をとらなければ、せっかく日本で作成した日本の公正証書遺言でさえも、タイ国内の財産に対しては法的効力が及ばず、無効となることがあります。
したがって、日本人がタイ国内に不動産や預貯金などの財産を所有している場合は、タイの法律に基づいて正式に作成された遺言書を現地で作ることが必須です。
目次
タイにおける遺言の作成条件
タイ国内で弁護士の立会いのもとに作成する必要があります。
作成にあたっては、偽造や改ざんを防ぐ目的から、実務上は「普通遺言」と「自筆証書遺言」を組み合わせた形式が一般的です。
遺言は、本人が自筆で作成しても、パソコンで出力した文書でも問題ありませんが、利害関係のない証人2名(未成年は不可)による署名が必要です。
作成された遺言書は、通常遺言執行者(多くの場合は弁護士)によって保管され、相続発生後の手続きにおいては、裁判所による認証を受けることが実務上不可欠となります。
遺言の有効性
遺言が有効と認められるためには、遺言者が正常な精神状態で意思を明確に表明していることが必須条件となります。
遺言書の署名日から3日以内に健康診断を受け、発行された診断書を遺言書とともに保管します。
これは、遺言の有効性を後日証明するための極めて重要な手続きです。
また、受益者(財産を受け取る人)が養子である場合には、タイ役所発行の養子縁組登録証の提示と確認が必要です。

遺言書作成に必要な書類
遺言書を作成する際には、以下の書類を準備する必要があります。
- 遺言者および受益者の身分証明書類
- パスポートの写し
- IDカードの写し
- 住居登録書(タビアンバーン)の写し
- 婚姻証明書および役所での記録書類 など
- 健康診断書(遺言者)
遺言者が作成時に正常な判断能力を有していたことを証明するための診断書です。 - 資産リスト(遺言者)
不動産、銀行預金、株式、車両など、遺言対象となる財産の一覧表を作成します。
参考)個人に対する相続税
以下は、個人に対する相続税・贈与税の納税義務者制度の分類の表(国税庁のWEBSITEから引用)です。ご参考に。
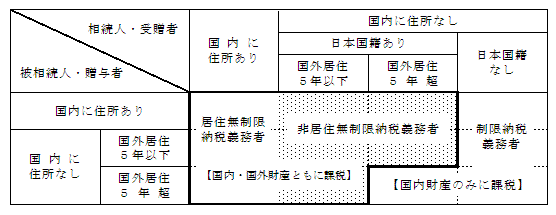
デジタル遺品の整理も必要~家族に迷いを残さないために
デジタル遺品とは、亡くなったあとに残る パソコン・スマートフォンのデータや インターネット上の契約・資産(SNS、ネット銀行、サブスク等)を指します。 放置すると個人情報の流出や不正利用、気づかないまま有料サービスの支払いが続くなどのトラブルにつながります。 これらは見えにくい「遺品」であるため、事前準備が重要です。
整理の第一歩:データの仕分け
見られたくないデータや個人的な情報は、あらかじめ削除するか、フォルダ分けしてパスワード保護しておきましょう。 また「この写真は残してほしい」「このSNSは削除してほしい」などの意思は、メモやエンディングノートに明確に記載します。
利用サービスの一覧を作る
日常で利用しているすべてのネットサービス(SNS、ネット銀行、サブスクリプション等)を洗い出し、次の情報をリスト化します。
- サービス名(例:〇〇銀行、△△SNS)
- ID・パスワード(保管場所の記載でも可)
- 問い合わせ先/アクセス方法(URL、サポート窓口など)
家族との情報共有
作成したリストやパスワードの保管場所は、信頼できるご家族に伝えておきましょう。 誰がどのサービスの解約・名義変更を担当するか、事前に役割分担を話し合って決めておくことが大切です。